
未経験から経理に転職するのに、簿記一級があると有利かな、、?
簿記以外にも取った方が良い資格には、何があるんだろう。。

資格については、悩みやすいポイントだよね!
自分も未経験から経理に転職して、採用責任者もやってたから、
その経験をもとに解説するよ!
未経験から経理に転職するには、簿記が必要だとよく言われます。
しかし、
悩むことも多いですよね。
結論から言うと、資格として簿記だけを取得するのであれば、2級(日商簿記)まで持っていれば十分で、1級(日商簿記)を持つことの転職活動への優位性は、それほど高くありません。
一方で、簿記以外に取っておくと転職に有利だったり、実務を遂行する上で役立ったりする資格はあります。
特に、経理以外の分野で、一定のキャリアを積んできた40代以上の方が、経理にキャリアチェンジしようとする場合は、重要です。
そこで本記事では、まず、簿記1級の資格を取得することの効果についてご説明した上で、経理業務に関連する全資格をリストアップし、転職活動に有利な資格について解説します。
私自身が、
を踏まえて、ご説明します。
なお、30代後半・40代以上でも、未経験で経理に転職できる包括的な戦略を下記にまとめていますので、併せてご参照ください。
簿記一級の資格があれば経理に未経験で転職できるか否かの実情
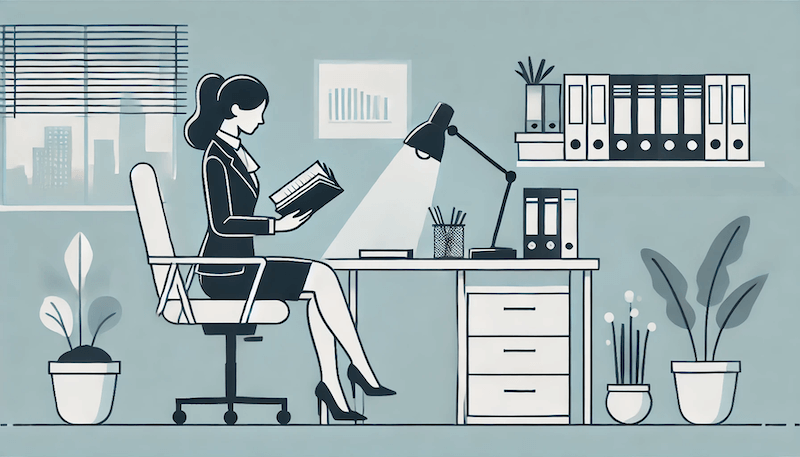
- 簿記1級と実務経験、どちらが重要?
- 40代・50代で経理未経験の場合、簿記1級の資格を取得する効果は?
- 簿記1級の資格を取るのは、やめとけという事か?
- 経理未経験でも簿記2級まではとりたい
- 簿記の学習方法は?独学も可能?
結論として、簿記1級(簿記一級)(※)を持っていれば、未経験で経理に転職できる訳ではありません。
逆に言うと、未経験での経理転職において、簿記1級は必須ではないのです。
以降では、私が管理部門長 兼 採用責任者として、経理担当者を採用してきた経験に基づき、その背景を詳しく説明していきます。
(※)本記事で表記する「簿記」の検定は、「日商簿記」を指すものとします。「日商簿記」は、「日本商工会議所 簿記検定試験」の略になります。この他に、全経簿記(全国経理教育協会 簿記能力検定)、全商簿記(全国商業高等学校協会 簿記実務検定試験)、日本ビジネス技能検定簿記能力検定、という3種類の簿記検定がありますが、ここでは最も一般的な日商簿記を代表として記載しています。
簿記1級と実務経験、どちらが重要?
結論としては、実務経験の方が重視されます。
その理由は、簿記1級レベルの知識を求められる場面が、企業によって大きく異なるためです。
簿記1級には、大企業・上場企業で用いられることが多い高度な連結会計の知識や、会社によって活用方法が大きく異なる意思決定会計(※)が含まれています。
(※) 戦略管理会計とも呼ばれ、投資や部門別採算判断など、経営者が決定を下すために必要な情報を提供するための会計を指します。
一方、簿記2級レベルまでの知識は、どの会社でも必要になるため、採用側としてはその知識を持っていることを前提に、早く手を動かして自社の実務に慣れてほしいと考えます。
従って、経理未経験であっても、簿記2級の知識があれば十分であり、まずは実務に入れる状態にしておく事が、転職においては重要となります。
40代・50代で経理未経験の場合、簿記1級の資格を取得する効果は?
結論として、40代・50代で経理未経験の場合、転職にあたって、簿記1級を取得する効果は小さいです。
年齢が高い分だけ、「難易度の高い簿記1級の保有が求められるのでは」と考えるかもしれませんが、実際は逆です。
採用担当者は、年長者には即戦力性を求めるため、できるだけ早く実務経験を積んでほしいと考えます。
また、簿記1級レベルの知識が求められる職場には、既に上位資格である公認会計士や税理士の資格保有者が在籍しているケースも多いです。
そのため、実務経験がなく、簿記1級だけを持っているという状況は、やや中途半端な印象になります。
もちろん、大企業の経理部門やスタートアップのCFO候補を視野に入れ、公認会計士や税理士の取得を目指す過程として、簿記1級を取得するのは有効ですが、これは既に経理実務経験のある方が目指す方針です。
したがって、簿記1級の勉強に時間をかけるよりも、できるだけ早く実務経験を積めるよう、社内での異動や転職を検討した方が良いでしょう。
簿記1級の資格を取るのは、やめとけという事か?
とは言え、簿記1級を取ること自体に価値がないかというと、そんな事はありません。
以降では、簿記1級の価値について、ご説明します。
簿記1級はどれくらいすごい資格か?
簿記1級は、商業簿記(小売業の会計処理)、工業簿記(製造業の原価計算)の深い知識から、意思決定会計(部門別採算評価、投資意思決定等)まで、幅広い知識を習得できるため、自信をもって会計の専門家と名乗れるレベルの資格と言えます。
特に、税理士試験の受験資格の1つに定められていたり(現在は、大学2年生以下が対象)、公認会計士を取る前の前哨戦として取得されることも多いため、そのレベルの高さがうかがえます。
簿記1級が難しい理由は?
簿記1級の取得が難しい大きな理由は、学習すべき量が膨大である点です。
簿記2級に必要な学習時間が100〜200時間と言われるのに対し、簿記1級には400〜600時間が必要と言われます。
これは1年間、毎日1時間以上の勉強が必要になる計算です。
また、簿記2級までの知識を数段深くした内容が問われるほか、試験時間も2級の倍(トータル3時間)あることや、2級にはなかった論述で解答する問題もあり、試験の形式としても難易度が高いです。
簿記1級を取得したら年収は増える?20代でも増える?
簿記1級の取得者は、簿記2級までの取得者に比べ、転職先から受けるオファー年収が高い傾向にあります。
20代でも、簿記1級取得者へのオファー年収は、平均で84万円ほど高く、全年代平均では149万円ほど高いというデータがあります。(出典:MS-Japan)
但し、注意点としては、簿記1級取得者の転職後の年収は、転職前の年収よりも平均で73万円ほど低いという点です。(出典:MS-Japan)
そのため、転職先企業は、必ずしも簿記1級の保有だけを評価している訳ではなく、実務に即したビジネススキルや経験を評価している事が分かります。
経理未経験でも簿記2級まではとりたい
簿記検定は、2級まで取得していれば十分ですが、3級だけだと心もとないです。
3級は、小売業をイメージした会計処理(商業簿記)を学びますが、2級は、これに加えて、製造業をイメージした「原価計算」(工業簿記)という概念を学びます。
そのため、製造業のように、原価計算が必要となる会社に就職した場合は、2級を勉強していないと苦労することになります。
また、ソフトウェアが絡むIT系の企業では、「ソフトウェア原価計算」を理解している必要があるため、成長分野であるIT系への転職を考えるなら、やはり2級の取得は必須となります。
簿記の学習方法は?独学も可能?

結論としては、簿記2級までであれば、独学でも可能です。
一方、1級は難しいと考えたほうが良いです。
理由は、1級は、2級と比べて格段に範囲が広くなり、市販テキストの冊数も膨大になり、学習のペースメークや演習の利便性という観点で、継続が難しいと想定されるためです。
現在は、オンラインで非常に安価に講座を受講できるため、2級までの取得であっても、簿記初心者の方は、オンライン講座の受講をオススメします。
格段に早く理解でき、効率的な学習が可能です。
おすすめの日商簿記オンライン講座
❏クレアール
「クレアール」は、老舗の簿記通信講座のスクールで、分かりやすく、安価で高い評判を誇っています。
特に、学習範囲を、試験に出るところに絞って徹底学習する「非常識合格法」は、本業で忙しい40代以上の方にとっては、大変魅力です。
また、初心者から2級の合格を目指すのであれば、3級と2級をセットで学習できる講座が、効率的でお勧めです。
日商簿記の2級と3級を同日に受験し、同時合格できた方は、私の同僚にもいましたので、決して無理ではないプランかと思います。
クレアールでは、「3・2級講義パック」が用意されており、3万円程度の価格で受講できます。
さらに驚きなのは、「2年間の受講保証」という、他には無い破格のサポート体制なので、
不合格になったら、またお金と時間がかかる、、、
という不安を払拭でき、安心して学習できるので、オススメです。
>> クレアール簿記アカデミー (公式サイト)を見る
❏スタディング
「スタディング」は、幅広い資格のオンライン講座を提供していますが、価格が非常に安く、また様々な学習機能を備えているサービスです。
特に、昨今のAIを活用し、最適な復習タイミングをAIが判断してくれる「AI問題復習機能」がある点も魅力です。
スタディングでは、3級・2級を同時学習できる「簿記3級・2級セットコース」を提供しており、他の講座では見られない、2万円程度という破格の価格で受講できるので、こちらもオススメです。
独学する場合のおすすめの参考書籍
どうしても費用を抑えたい、という方には、資格学校のTAC出版が出している
がオススメです。
市販のテキストは、どれも分かりやすいのですが、このシリーズをオススメする理由は、
テキストと問題集が一体化している
という点です。
とにかく勉強するには、本の冊数が少ない方がハンドリングしやすく、学習もはかどりやすいです。
私も過去、愛用していました。
この「スッキリわかる」シリーズであれば、日商簿記2級の学習が、商業簿記、工業簿記で合計2冊(予想問題集を追加しても合計3冊)で済みますので、持ち歩くのも便利です。
簿記一級よりも経理に未経験で転職する際に有利になる資格:40代・50代向け
以降では、経理業務に関連する全資格をリストアップした上で、経理以外の分野で一定のキャリアを積んできた40代以上の方にとって、転職活動上、有利に働く資格について解説します。
- 経理の資格には、どんなものがある?
- 40代以上の経理実務未経験者に役立つ資格は?
- 経理未経験者に他の検定試験は必要?
- 簿記以外の資格は、いつ取得すべきか?
- 経理未経験での資格取得にはオンライン講座がおすすめ
経理の資格には、どんなものがある?
以下に、経理の仕事に関連する、主な資格をリストアップしました。
メジャーなのは、検定試験と国家資格になりますが、米国公認会計士などの外資向け資格や、建設業経理検定などの特定業界向けの資格もある点が、特徴的です。
❏ 検定試験
- 日商簿記(1級・2級・3級)(※)
- ビジネス会計検定(1級・2級・3級)
- 電子会計実務検定(1級・2級・3級)
- 給与計算実務能力検定(1級・2級)
- 経理・財務スキル検定(FASS)
- 経理事務パスポート検定(PASS:1級・2級・3級)
- 消費税法能力検定(1級・2級・3級)
- 財務報告実務検定
- IPO実務検定(標準、上級)
(※再掲)「日本商工会議所 簿記検定試験」の略。この他に、全経簿記(全国経理教育協会 簿記能力検定)、全商簿記(全国商業高等学校協会 簿記実務検定試験)、日本ビジネス技能検定簿記能力検定、という3種類の簿記検定がありますが、ここでは最も一般的な日商簿記を代表として記載しています。
❏国家資格
- 公認会計士
- 税理士
- 中小企業診断士
- 社会保険労務士
- ファイナンシャル・プランナー(FP技能士)(1級・2級・3級)
❏外資向け資格
東京商工会議所主催の「BATIC」(国際会計検定)®という検定もありましたが、2022年度の第44回試験をもって終了したため、現在は受験できません。
❏業界別資格
- 銀行業務検定(11の種目別に級を設定)
- 社会福祉法人経営実務検定(入門、会計1級・2級・3級、経営管理)
- 農業簿記検定(1級・2級・3級)
- 建設業経理検定(1級・2級・3級・4級)
40代以上の経理実務未経験者に役立つ資格は?
基本的には、日商簿記2級と、実務経験の蓄積で十分ですが、本サイトで、転職先候補としてお勧めしている
「IT系中小企業」の経理職(※)
への転職を目指すにあたり、役立つ資格を、私自身の経験も踏まえてご紹介します。
(※)ここで言う「IT系」とは、銀行や官公庁向けの大規模システムを開発する「SIer」ではなく、インターネットを基盤としたWebやアプリのサービスを運営している、いわゆる「ITベンチャー」を指しています。
具体的には、
になります。
税理士試験の科目合格(会計科目:簿記論・財務諸表論)
税理士試験は、全5科目(会計科目2科目、税法科目3科目)に合格する必要がありますが、このうち会計科目の2科目(簿記論・財務諸表論)の合格を目指します。
簿記論・財務諸表論の有益性・合格難易度
実際の企業で求められる簿記・財務諸表作成に関わるほぼ全ての知識を習得することができ、実務に役立つ場面が多くあります。
一方で、原価計算の領域は含まれていないため、公認会計士ほど難易度が高くなく、仕事をしながらでも合格することが十分可能です。
実際、私も仕事をしながら、この2科目に合格できました。
各科目、1年ずつ勉強すれば十分合格できる試験です。
また、互いに関連性が強い科目なので、時間の取れる方であれば、同時に学習して、2科目同時に合格される方も少なくありません。
科目合格の権利は生涯保持されるため、いつでも残り3科目にチャレンジし、最終的に税理士資格の取得を目指すことができます。
この点は、公認会計士試験とは異なり、とても取り組みやすい点です。
注目すべきポイントは、令和5年度から、「簿記論」と「財務諸表論」については、受験資格が撤廃されたことです。
これまでは、「日商簿記1級」か「全経簿記上級」の合格、または大学での「法律学又は 経済学」に属す る科目の単位取得が必要でした。
ここで、「会計科目だけ取るので良いの?」と疑問を持たれるかもしれません。
もちろん、税法科目を含めた5科目全てに合格できると良いのですが、中小企業では、大企業と異なり、リソースも限られるため、税務申告を自社でやることはほぼなく、顧問となる税理士事務所に委託する事が一般的です。
そのため、税法の深い知識まで求められることはありません。
また、税法科目は難易度が高く、市販教材も少ないため、独学で合格することは不可能に近いです。
年齢も踏まえると、時間対効果、費用対効果を考慮して判断する必要があります。
オンライン講座での学習で合格できる
税理士試験は今、とても安価に勉強できます。
「スタディング」のオンライン講座を活用すると、なんと簿記論と財務諸表論の2科目をセットで7万円程度の金額で受講できます。
以前は、完全に独学で頑張るか、資格学校に、各教科に20万円程度を支払って勉強するしか方法がなかったのですが、オンラインで数万円で勉強できるようになりました。
本当に便利な世の中になりました。
「スタディング」には、私自身も大変お世話になりました。
特に、「理論暗記ツール」という「スタディング」でしか見たことのない暗記学習が効率的にできる独自ツールが提供されており、重宝しました。
是非、講座の詳細については、以下のリンクからご確認ください。
中小企業診断士
中小企業に対する経営コンサルタントとして、幅広くビジネス知識を身につけられる資格です。
受験科目は、以下の構成になっています。
中小企業診断士の有益性
本サイトで、未経験者向けにお勧めしている
経理周辺の職種でスタートし、そこで経理業務の一部を兼務しながら、経理職を目指す
という戦略で進める上では、経営戦略、組織人事、法務、情報システムなど、バックオフィス領域の幅広い知識を身につけられる点は、大きな魅力です。
会計スキルが強化される
「財務・会計」という科目には、税理士試験における「簿記論」・「財務諸表論」に該当する分野のほか、「日商簿記1級」や「公認会計士試験」で求められる原価計算、意思決定会計の分野も含まれます。
あくまで、企業に経営面でのアドバイスをする事を目的とした知識習得なので、「日商簿記1級」や、会計監査を目的とした「公認会計士試験」ほど、難易度は高くありません。
そのため、日商簿記2級でしか学べなかった原価計算の領域を、より深く学ぶのに、ちょうどいいレベルとなります。
また、企業の財務諸表を診断する財務諸表分析や、管理会計(部門別の損益計算方法など)も学べる点も大変有益です。
経営目線での提案力がつく
40代以上という年齢を踏まえると、単に経理業務を遂行できるだけでなく、過去のビジネス経験も踏まえ、経営目線で、会社に提案できるスタンスが求められます。
その意味では、体系的なビジネス知識に基づく提案ができるようになるので、年齢にもふさわしく、実務に直結する資格だと思います。
事実、私が経営企画を担当していた時に、習得した知識は大変役に立ちました。
経営企画は、単に「数字がこうだった」という結果だけでなく、そこから「何が言えるか」、「どうすべきか」を提案する事が求められるためです。
【経験談】私が採用される側だったときの経験を思い出すと、中小企業を受ける際、この資格を持っていると、面接官の方に、必ず興味を持ってもらえた実感があります。
「自社の経営規模に適した知見を持っているのでは」と期待されるからだと思いますが、このように選考でチャンスに繋がりやすい点も、取得を目指すメリットになります。
中小企業診断士の合格難易度
難易度は低くはありませんが、公認会計士試験のように、資格取得に全力投球が求められるほどではありません。
特段の受験資格はなく、順調に行けば、1次試験の合格までに1年間、2次試験の合格に更に1年間の計2年間の勉強で、合格することが可能です。
また、1次試験で合格した科目の権利は、翌々年まで持ち越せるので(合格した科目は、2年後の試験まで受験を免除できる)、仕事をしながら十分取得が可能です。
私も仕事をしながら勉強し、何とか合格できました(2次試験で苦戦し、数年かかりましたが、、)。
オンライン講座での学習で合格できる
こちらも「スタディング」のオンライン講座を活用すれば、5万円程度から1次試験・2次試験の講座を受講できます。
資格学校に通うと、30万円程度かかるケースもあるため、それに比べると、破格の安さです。
1次試験は、市販テキストでの独学でも可能ですが、2次試験は論述式のため、講座を受講して学習する事をオススメします。
経理未経験者に他の検定試験は必要?
外資系企業への転職や、特定業界(建設業界など)への転職を想定されている場合には、前述で挙げた「米国公認会計士」や「建設業経理検定」などを取得されることは転職活動に有利に働きますが、ここでは、一般的な日本企業の経理職に転職する場合を想定してご説明します。
ご自身の理解を深める、という観点からは、
- 給与計算実務能力検定
- 経理・財務スキル検定(FASS)
- 経理事務パスポート検定(PASS)
などを取得する意味は、十分あると思います。
一方で、未経験からの経理転職で有利になるか、というと、経理担当者を採用してきた採用責任者・管理部門責任者の立場からは、
有利になる可能性は低い
と考えます。
理由は、経理実務の方法は企業によっても異なるため、知識面は、日商簿記2級程度で十分なので、その知識をベースに、早くその企業に合った実務を習得してもらいたい、と考えるためです。
採用担当者の目に留まるレベルの資格、というのは、やはり難易度が高いとされる国家資格になります。
そのため、日商簿記2級を取得したら、早く転職活動を開始されることをお勧めします。
もちろん、時間に余裕があり、よりご自身の知識を深めたい場合には、他の検定資格の取得を検討されても良いでしょう。
簿記以外の資格は、いつ取得すべきか?

ここまでご覧になられた方で、税理士(科目合格)や、中小企業診断士を取ってから転職するとなると、とても時間がかかるのでは、、、と心配された方もいらっしゃるかもしれません。
結論、これらの資格を取得するのは、転職してからで大丈夫です!
ただ、できれば学習だけは始めておいて、転職の面接段階で、「チャレンジを予定している」、「勉強を始めている」、という事が伝えられると、採用担当者にはポジティブに映ります。
年齢も踏まえると、早く実務経験を積むことの方が重要になりますので、基本戦略としては、
- 転職前に日商簿記2級を取得する
- 転職活動を行う(できれば国家資格の勉強を始めておく)
- 転職後、国家資格を勉強しながら実務に従事する
という流れになります。
この戦略が、最も費用・時間対効果が最大化されると考えます。
国家資格については、仮に取得できなくても、難易度が高い分、勉強しただけでも確実に実務に活きるので、無駄にならない点もメリットです。
経理未経験での資格取得にはオンライン講座がおすすめ
教室に通うスクール形式の講座は、集中できる環境で勉強できる点がメリットですが、やはり本業がある会社員には、移動時間が最大のデメリットになります。
その点、オンライン講座は、自宅だけでなく、通勤途中のスキマ時間も活用でき、忙しい会社員には最適な受講方法です。
また、講座品質の面においても、昨今のオンライン講座は、情報のアップデート・講座内容の改訂が頻繁に行われ、スクール形式と同等のレベルに上がっています。
講義資料も電子ファイルで提供されるので、演習用の解答用紙を何度も印刷できるなど、利便性が高いです。
「スタディング(STUDYing)」は、元々「通勤講座」という名前で提供されていたオンライン講座のサービスで、その名のとおり、スキマ時間を最大限活用できるように設計されているサービスです(2018年に「スタディング」にブランド名変更されました)。
私自身、「通勤講座」時代から「なんて便利なサービスなんだ!」と思い、日々、お世話になっていました。
何より、費用が従前のスクール形式に比べて大幅に安価なため、有り難いです。
「スタディング」は、受講できる資格講座のラインナップも非常に広いので、本記事でご紹介した
をいずれも受講できます。
具体的な学習方法や講座の内容については、以下のリンクからご確認いただけます。
「無料登録」をすれば、各教材を無料でお試しもできますので、是非、興味のある資格について、登録されることをオススメします。
資格の学習・取得を通じて、是非、知識面での自信をつけながら、転職活動に望みましょう!
簿記一級の未経験での経理転職への必要性と簿記以外で有利な資格について総括
本記事のポイントを、以下にまとめます。
本記事が、皆さんの転職活動のご参考になれば幸いです。



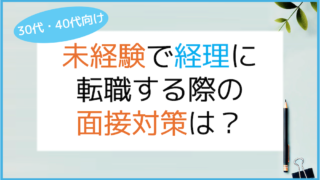
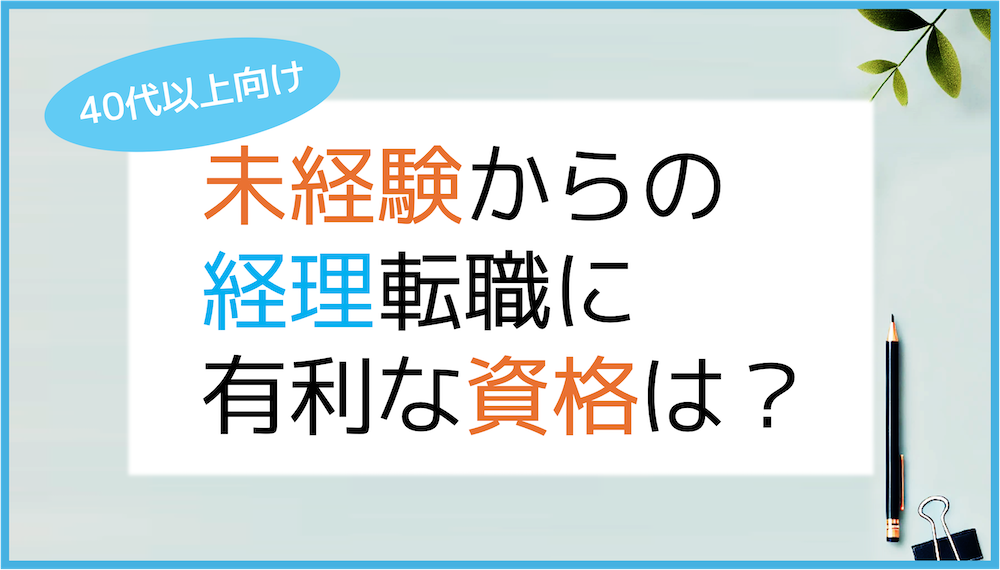







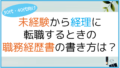
コメント