
今後、AIの活用で将来経理の仕事がなくなるって本当かな、、、?
経理職に転職したいけど、将来性とか大丈夫かな。。

大丈夫!経理の仕事はなくならないよ!
逆に、AIを活用できないとマズイから、その方法を解説するね!
これから未経験で経理職への転職を目指す方にとって、ChatGPTに代表される、昨今の目覚ましい生成AIの発展により、
「そもそも経理の仕事がなくなってしまうのでは?」
「本当に経理を目指して大丈夫かな、、、」
と不安にかられ、悩む方も多いですよね。。
結論から言うと、
AIが、経理の仕事を完全に奪うことはありません。
実は、経理業務の基本的な部分こそ、AIに奪われにくいのです。
もちろん、AIでなくなる仕事も存在します。そのため、危機感を持つことは必要ですが、本当に重要なのは、仕事が奪われるかどうかではなく、
AIをどのように活用できるか
という点です。
今後、AIを活用できない経理担当者は、仕事が遅く、生産性が低いと判断され、淘汰される恐れがあります。
逆に言えば、AIを味方につけて積極的に活用することで、他の経理人材よりも付加価値の高い仕事を行い、自分を差別化できます。
本記事では、私がアラフォー・未経験で経理職に転職した結果、複数社で12年以上にわたり、経理を含めたバックオフィスの責任者(管理部長)を務めてきた経験と、生成AIを日々の業務に活用してきた経験をもとに、以下の内容を解説します。
未経験から経理職を目指す皆さんが、より安心して転職活動に望んでいただけるためのご参考になれば幸いです。
なお、30代後半・40代以上でも、未経験で経理に転職できる包括的な戦略を下記にまとめていますので、併せてご参照ください。
若い年齢の方々でも、この戦略を身につけることで、若さに加えて、更に転職活動を有利に進めることができます。
AIがあっても経理の仕事がなくならない理由
冒頭でもお話した通り、経理の仕事はそう簡単にはなくなりません。
経理業務にはAIではカバーしきれない部分が多く存在します。
ここでは、私自身の経理業務の実体験を踏まえ、具体例を挙げてご説明します。
非定型的情報に基づく判断が必要だから
私が、経理実務に従事して実感したのは、経理業務のコアスキルは、
であるという点です。
一見、単純に見える仕訳の入力作業でも、実際には既存取引の背景情報や特殊性、新規取引の発生情報などを把握していないと、適切な仕訳を行うことが難しいです。
たとえば、同じような入金処理であっても、事業のビジネスモデル・商流によって、処理方法が異なります。
ある場合には、売上として計上すべきですが、別の場合では、預り金として扱うべきだったり、立替金の消し込みとして処理する必要がある場合もあります。
このような違いを理解し、臨機応変かつ適切に判断することが求められます。
この判断の部分は、日々変化する事業状況(ストーリー)や、今後の経営方針などを深く理解している人間でなければ対応できません。
AIは膨大なデータを分析することは得意ですが、非定型的な情報に基づく判断は、まだまだ人間にしかできない領域です。
また、事業担当者との定期的なコミュニケーションを通じて、最新の情報を得ることも重要です。
こうした日々のやり取りから得られる情報が、経理業務の正確さと信頼性を支える基礎となります。
最後の砦としてミスの許されない仕事だから
経理の業務には、納税額の計算、取引先への支払い、社員の給与支払いなど、ミスが許されない重要な業務が多くあります。
これらの作業でミスが発生すると、修正できたとしても、その過程で余計なコストや手間がかかります。
例えば、修正した金額で再振込を行うためには、取引先への連絡や、追加の振込手数料が必要です。
退職した社員に、誤って多めの給与を支払ってしまった場合は、その差額を返金してもらう必要が生じ、場合によっては、大きな問題に発展することもあります。
AIに「たたき台」を作ってもらう分には有益なのですが、最終的な確認と責任を担うのは、やはり人間です。
AIの精度が向上しているとはいえ、最終確認をAIに任せることに、不安を感じる人は多いでしょう。
仮に、部下から
「自分は見てません。でも、AIに確認してもらったので大丈夫です!」
と言われて、安心できる社長や上司は、どれだけいるでしょうか。。
時代と共にこの状況は変化する可能性がありますが、現時点では、AIに責任を負わせることはできません。
最後の砦として、責任を取らなければならない経理の仕事は、引き続き、経理担当者が担うことになります。
社内外の人とのやり取りが必要だから
経理の実務現場では、受け取った証憑(請求書などの会計処理の根拠資料)に間違いがあったり、突然イレギュラーな状況が発生したりすることが頻繁にあります。
これに対応するためには、社内外の人と、様々な調整が必要になります。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
こうしたやり取りは、日常茶飯事で発生します。
簡単に原因を突き止められないと、これらの業務に対応するだけで、一日の大半の時間が消費されてしまうこともあります。
私自身、日々の業務の中で生成AIをフル活用していますが、こうした社内外とのやり取りに関しては、どうしても人間が担う必要があると実感しています。。。
どんなに効率化しても経理業務をゼロにはできないから
例えば、小規模の会社の経理業務を、1名の経理担当者と社長、または顧問税理士と社長、という体制で運営していた場合、その社長が
「これからはChatGPTにすべて任せるぞ!」
と言って、経理担当者を辞めさせたり、顧問税理士との契約を終了したりするでしょうか?
どんなにChatGPTに業務を任せたとしても、
- 生成AIを使うための設定やプロンプトの入力
- 会計システム側の設定
- 最終的な結果のチェック
など、一部の業務はどうしても人間が行わなければなりません。
経理担当者や顧問税理士がいなくなれば、社長自身がこれらの対応を行うことになり、かえって仕事が増えてしまいます。
そのため、結局のところ、
生成AIを活用して経理業務を遂行できる人材
は、引き続き必要になるのです。
しかし、AIの存在により、今までよりも多くの業務をこなすことが期待されるため、経理人材に求められる能力も大きく変わってきます。
この点は、経理人材の生き残り戦略として、非常に重要なポイントなので、後で詳しくご説明します。
AIでなくなる経理の仕事もたくさんある
もちろん、経理担当者が、危機感を持たなくてよい訳ではありません。
経理の仕事の一部は、確実に生成AIに奪われることになります。
特に、経理業務においては、
100%の精度を求めないが、とりあえず「たたき台」を作ってほしい
というタイプの仕事は、非常にAIに向いています。
経理担当者のキャリアが、次のような仕事に依存している場合は、将来的にその仕事がなくなる可能性があるため、注意が必要です。
別の人に確認・修正してもらうことが前提での仕訳入力
たとえば、
- 請求書や領収書を見ながら、とりあえず仕訳を入力するが、
- 後で熟練の担当者(上司や正社員の経理担当)がチェックし、間違っていたら修正してもらえる
といった、責任レベルの低い業務は、AIに取って代わられる可能性が高いです。
既に、「マネーフォワードクラウド会計」や「freee会計」などのAI搭載のクラウド会計システムでは、クレジットカードやネットバンクから、自動で取引情報を読み込み、AIが仕訳の「たたき台」を作成してくれます。
この仕訳は、最終的に経理担当者がチェックし、適宜修正することが前提です。
そのため、今後の経理担当者は、単に仕訳入力を行う側ではなく、少なくともチェックを行う側に回らなければ、経理の仕事に従事し続けるのが難しくなることを認識する必要があります。
財務分析や改善施策の提言
貸借対照表(BS)や損益計算書(PL)などの財務諸表を見て、経営状況の分析コメントや改善施策の提案コメントを作成する業務も、AIが得意とする分野のため、取って代わられる可能性が高いです。
一見すると、数字から示唆や提案を導くというのは、人間にしかできない付加価値の高い仕事のように思えます。
しかし、分析系・提案系の仕事は、一発で正確な結論を出す必要はなく、「たたき台」レベルのレポートを作成してもらえれば、十分に価値があります。
即時に100%の精度を求められるわけでもなく、最後の砦として、絶対にミスを防がなければならない性質のものではないため、AIに適している業務なのです。
そのため、前述の仕訳業務の話と同様に、誰かがチェック・修正してくれる前提で分析・提言するのではなく、分析・提言を自ら責任もってプレゼンテーションする立場になる必要があります。
経理で生成AIを活用する方法
今後の人手不足が深刻化していく時代では、少人数で多くのアウトプットを出せる能力が必要です。
経理担当者にも、そのような姿勢が求められます。
そこで重要になってくるのが、
AIをどう自分の武器にするか
という視点です。
本記事の執筆時点では、様々な生成AIが存在していますが、ここでは最も機能の質と幅に優れているとされる「ChatGPT」の使用を前提に、経理業務へのAI活用法をご説明します。
これから経理への転職を目指す方にとっては、理解しづらい面もあるかと思いますが、転職後のAI活用イメージとして、是非ご参考にしてください。
一部の内容は、転職前であっても、ダミーの情報をご自身で作成して、ChatGPT無料版で実験してみることも可能です。
事前に使った経験があれば、転職後すぐに「AIに詳しい経理」として、一目置かれる存在になれますよ!
以降の内容は、経理職として入社した会社が、「ChatGPT Team」や、それ以上のプラン(本記事執筆時点では「ChatGPT Enterprise」のみ)を契約している場合を前提にしています。
ChatGPTの無料版または「ChatGPT Plus」(個人アカウントでの有料版)でも利用自体は可能ですが、これらのプランでは、ChatGPTに入力した機密情報が、ChatGPTの学習に利用され、情報漏洩のリスクがあるためです。
無料版や「ChatGPT Plus」では、機密情報の入力は避け、入力するデータは、ダミー情報にするよう留意してください。
Excel VBA(マクロ)のコード作成
経理担当者に、よく使われている用途の1つです。
経理業務では、大量のデータを扱うために、Excelのマクロを使い、処理を自動化する事があります。
マクロを動かすには、VBA(Visual Basic for Applications)のコードを書く必要がありますが、これをChatGPTに書いてもらうことができます。
ネットで調べながら、コードを自作しても良いのですが、
「●●のセルから、〜の計算をしたものを、〜のシートの■■セルに出力するExcel VBAのコードを作成してください」
みたいな感じで指示すれば、適切なコードを書いてくれるので、ネットで調べるよりも遥かにラクです。
プログラミングのコード作成は、ChatGPTにとても向いているタスクなので、私もよく使用させてもらっています。
仕訳入力内容のチェック
経理業務では、直近月の仕訳をひと通り入力した後、先月分や昨年同月分のデータと比較して、
などをチェックすることが一般的です。
この作業をChatGPTに代行させることが可能です。
具体的には、今月、先月、昨年同月の試算表(勘定科目別の金額が分かる表)を、ChatGPTに読み込ませて、異常値や変化が大きい点を指摘させることで、より効率的にチェックを行うことができます。
このチェック作業は、経理担当者として、最後の砦となる重要な仕事なので、ChatGPTの確認結果に全面的に頼る事はできませんが、自分で行ったチェックに加え、ChatGPTにも指摘してもらうことで、見落としを補完できます。
経営数字の分析
経理担当者は、毎月の取締役会に向けて、月次決算の結果を報告しますが、同時に、自社の経営数字の状況を分析し、特筆すべき点があれば、併せて報告する事が求められます。
月次決算を終えた後、限られた時間で財務情報を読み込み、ゼロからコメントを考えるのは、労力がかかる作業です。
そこで、作成した貸借対照表(BS)や損益計算書(PL)をChatGPTに読み込ませ、「たたき台」となる分析コメントを生成してもらうことで、負担を減らすことができます。
もしくは、分析自体は自分で行い、その結果を粗く箇条書きした上でChatGPTに読み込ませ、レポート形式で清書してもらう、というのも有益な方法です。
「分析は好きだけど、文章にするのが苦手」
という人も多いと思いますが、分かりやすい文章を作るのは、生成AIの真骨頂なので、最も効果的な活用法の1つと言えます。
データの変換処理
会計システムには、仕訳データをインポートする機能がありますが、その準備として、売上や費用の取引データを、仕訳データの形式に変換しなければならない事が多々あります。
このようなデータ変換の作業を、ChatGPTに任せることも可能です。
例えば、取引先ごとに支払データが1行ずつあるテーブルを、1つの取引先あたり、3行の仕訳データに変換したい、といったケースが考えられます。
ChatGPTに、この変換作業を依頼することで、Excel作業の手間を省くことができます。
下図は、実際にダミーデータで変換作業を依頼した結果です(実際の業務では、もっと列数の多いデータになりますが、例示のため大幅に簡略化しています)。

※本体の取引額と調整額とに分けて、税込額で表示する変換もしてくれています
プロンプト(ChatGPTへの指示文)は、実際に人に説明する時と同様に、一例を示して、「他のデータもこれと同じルールでお願い」という感じで書けば、要領を掴んで対応してくれます。
こんな処理も精度高くやってくれるので、とても助かります。
ただし、ChatGPTの作業結果はあくまで「たたき台」なので、全てのデータが正しく変換されているか、確認する必要はあります。
この点が、自分でExcelで関数を組んで、変換フォーマットを作った場合に比べると、手間になります。
大量のデータに対して行う場合は、かえってチェックの方が大変になり、適さないかもしれません。
自分で変換したり、変換フォーマットを作成したりするのが面倒だけど、ChatGPTの出力結果を目視でチェックできる程度のデータ量、という場合には有効です。
以上の他に、請求書や領収書などの文書から、金額情報を読み取り、振込先毎の一覧表を銀行振込用に作成する、といった場合にも活用したいのですが、試した感触では、まだChatGPTの日本語のOCR(光学文字認識)機能の精度が高くない印象です。
AIは日々、改良されていますので、今後、精度が高くなってきたら、是非活用したいと思っています。
生成AIに負けないスキルの習得法
より強い経理人材になるためには、AIを使いこなすことに加えて、
絶対にAIにはできない業務にも強くなる
ことが不可欠です。
その一例として挙げられるのが、
経理に関わる業務改革を立案し、新しい仕組みの導入や運用改善を主導できるようになること
です。こうしたプロジェクトマネジメント力は、AIにはできない貴重なスキルです。
特に、どの企業の経理部門も抱える課題の一つに、
事業の拡大に伴う規模拡大への対応
があります。
具体的には、以下のような状況が想定されます。
企業が、規模拡大を目指して事業運営を行う以上、この問題は避けて通れません。
大企業であったとしても、特定の部署が立ち上げた新規事業で取引規模が急拡大することで、同様の課題が発生することがあります。
対策の中身自体は、Excelを使った方法、クラウドサービスの導入、外注化、いずれでも良いと思いますが、重要なのは、
業務上の課題を整理した上で、最適な対策を比較検討し、導入・運用まで担った経験
です。
もし、過去に規模拡大への対応経験がない場合は、現在の職場・部署で、同様の課題を見つけ、提案・実行することで、経験を積むと良いでしょう。
一般的に、経理担当者は、現状の業務を回すだけで手一杯なので、
定型作業だけでなく、企画や改善ができる人材
は貴重です。
そうした人材になれれば、企業も是非採用したいと考えるので、AIが進展する世の中でも、有利に転職できます。
生成AI講座の受講もおすすめ
まずは、ChatGPTの無料プランでも構いませんので、日頃から、積極的に生成AIを活用することをお勧めします。
さらに、より実践的に学びたい場合は、生成AIの活用方法を基礎から学べる講座もあります。
「DMM 生成AI CAMP」は、最短4週間で、ビジネスの現場で活かせる生成AI技術を習得できるオンライン講座です。
忙しいビジネスマンが、基礎から習得するのに適しています。
特に、この講座は「経済産業省 リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の認定講座であり、リスキリング補助金により、受講料の最大70%がキャッシュバックされる点は非常に魅力的です。
他の経理志望者と差別化したスキルを身につけたい方は、以下のボタンから、まずは無料相談をしてみましょう。
転職活動時に有利なだけでなく、「生成AIに詳しい経理」として、入社後も一目置かれる存在になれるので、経理未経験でも十分リカバリーできますよ!
経理の仕事はAIで将来なくなるか・なくならないか、について総括
経理の仕事が、AIによって完全になくなることはありませんが、生成AIの進化により、一部の業務が取って代わられる可能性はあります。
そのため、経理担当者は、生成AIを活用し、さらに生成AIに負けないスキルを身につけることが、重要になります。
AIを味方にして業務を効率化しつつ、業務改革等のプロジェクトを主導し、AIにはできない分野で力を発揮することが、経理人材としての価値を高める鍵となります。これは、経理に転職する前からでも習得が可能です。
そのために、生成AIの基礎を学びたい方には、専門的な講座の受講もおすすめです。
今後も進化し続けるAI技術を上手に取り入れ、他の応募者・経理担当者と差別化を図りながら、経理転職の成功と、更なるキャリアアップを目指していきましょう!



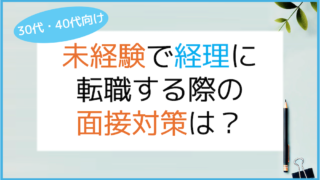
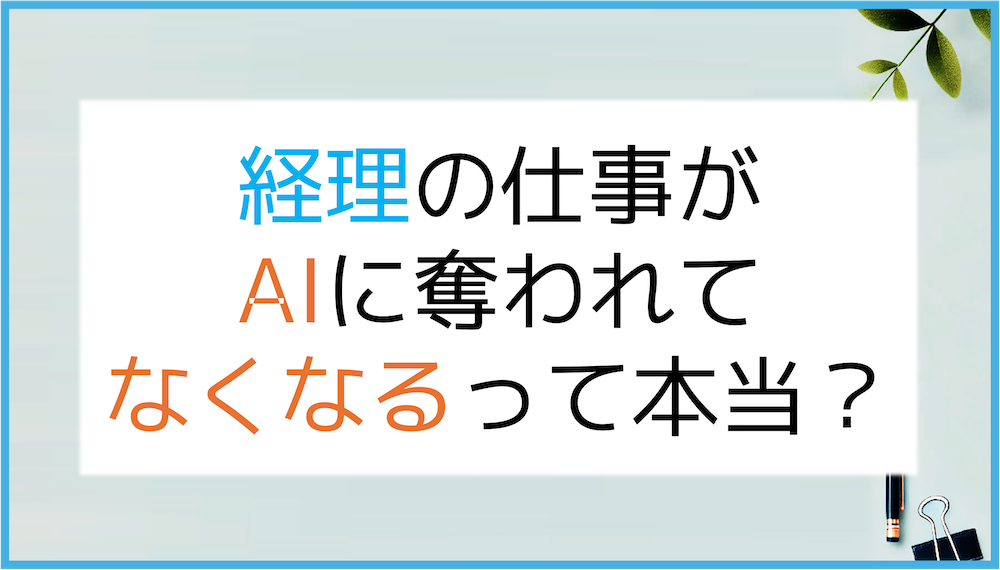






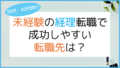

コメント